 |
大阪国立国際美術館 『現代美術の皮膚』 |
物心付いた頃から自宅で金魚を飼っていたが、金魚が死んで浮かんでいたのをどうしても手で触れられなかったことを思い出した。平気でバッタの脚や胴体を引きちぎって遊んでいた頃の話だから、成長してからカエルやバッタがかつてのように触れなくなってしまったのとは訳が違う。むしろ逆に今だったら生活を共にした感謝の表しとして最期に触れてあげるくらいのことは当然だと思うし、だからなぜ当時それができなかったんだろうと考えた。「気持ちが悪かった」というのは当時はそれを表現する語彙が足らなかったからだ。今改めて言うとすれば、それは、命が終わり生物から物質へと還ろうと外界へ溶けていこうとするその皮膚と触れ合うことによって、それが伝搬し自分の皮膚も共に外界へ溶けてしまうように感じたことに対する怖れだったのかもしれない。
このことは「皮膚」という概念の、2つの大きな意味を示唆する。1つは、生命を形作り、内に宿す生命を守り、その死とともに崩壊することから意味づけられる「生命体」と「外界」の境界面、即ち「生命」と「非生命」、あるいは「生」と「死」、「精神」と「物質」の境界。もう1つは、それらが触れ合うことが最も原始的かつ濃密な情報伝達手段であると誰もが本能的に知っているということ、即ち「自己」と「世界」、あるいは「自己」と「他者」の境界としての「皮膚」。
そんなギリギリの境界を探るテーマからして、必然的にグロテスクな表現によって鑑賞者の「生理的限界」という境界を暴くような作品が予期されるが、近くで直視できなかったのは玉虫で構成されたドレスくらいで、思ったよりも「キレイ」な作品が多かったというのは正直な感想。
皮膚というテーマに対して、それが自己と他者の絶対不可侵な境界であり、しかしだからこそ可能な限り寄り添いその温もりを感じていたいという欲求(もちろんそこには皮膚の一部としての性器による「触れ合い」も同列として含まれている)はもはや素直に認められ、かつては有機体としての肉体に拘束された人間の物理的限界を超えることに絶対的価値が見出された「機械」も、むしろその肉体が本来求める原始的欲求を満たすためだけに存在しても良い時代に来たことを告げているように思う。僕たちは所詮絶対的な孤独は超えられない。けど、だからこそ、その孤独を認めた上で可能な限り寄り添い、触れ合い、その小さな小さなコミュニティの中で美しく生きていこうという囁きが聞こえる。
 |
| 小谷元彦 『SP2 New born ViperA』 |
小谷元彦の、生物の骨格見本を思わせる一連の作品群には、しかし生命としての必要な機能的部分が何もない。主にカルシウム分で構成される骨は物理的にも有機物ではないし、トゲトゲしいディテールは一般的にも有機的形態とは言い難い。それでもそこに確かに有機体としての生命を感じるのは、それがかつて有機的で柔らかな皮膚に覆われた生命として生きてきた記憶を宿すからだろう。それはきっと、どれだけそれがリアルであっても、キメラやエイリアンの剥製や模型では感じることはできない。
以前に六本木で見た中村哲也の「速そうな形態」としてマシーンエイジの造形言語を抽象化した作品と重なるが、そこから読み取れるのは、小谷元彦の作品が、マシーンエイジの終焉を迎える次の時代の、新しい造形言語の可能性。
次の時代に求められる生き方。そしてそれを表現する造形言語。その声はまだ小さく弱々しいものだが、確かに耳に届いた今、これから自分の中でどう育っていくのか楽しみだ。
COMMENT AND SHARE
TRACKBACK PINGS
TRACKBACK URL:
http://www.k-en.net/blog3/mt-tb.cgi/4















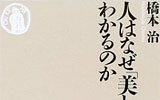


COMMENT
POST A COMMENT